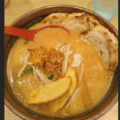乳幼児期の豊かな人間関係を育む遊び場面や保育を具体的なエピソードや事例を示して述べなさい。 その際に、留意すべき保育者の役割や援助の仕方について述べなさい。
幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期である。この時期の情緒的・知的な発達や社会性の育成は、遊びや生活といった具体的な体験を通して進められる。幼児の人間関係は、家庭での保護者との関係を基盤として形成されるが、次第に同年齢の友達や家族以外の大人の存在に気づき、関わりを求めるようになる。初めは同じ場所で別々に活動することに満足するが、やがて一緒に遊び、言葉や物のやり取りを行う中で、自己主張のぶつかり合いや互いに折り合いを付ける経験を重ね、友達関係を深め広げていく。幼児期の保育においては、領域「人間関係」において、工夫や協力を通じて一緒に活動する楽しさを味わうことが重要なねらいとして示されている。
具体的な遊び場面として、まず砂場での「ケーキ屋さんごっこ」が挙げられる。この遊びでは、役割分担として「作る人」「売る人」「客」などが自然に生まれるが、「私が作りたい」「僕が売りたい」といった自己主張の衝突が起こることがある。こうした葛藤を経験する中で、子どもたちは交代制や協力して大きなケーキを作るなどの方法を模索し、「譲る」「待つ」「協力する」といった社会性を身に付ける。このような体験は、自己中心的な思考から脱却し、相手の立場を理解しようとする発達段階の特徴を反映している。
次に、段ボールを用いた協同活動は、幼児期後半の協同性育成に有効である。子どもたちは家のイメージを描き、作業の手順や段取りを考えながら、言葉や身体表現で相手に自分の意図を伝え、相手の意図を理解しようとする。こうしたやり取りを通して、自己抑制や役割遂行の能力が養われ、完成後には達成感と友達への親密感を共有することができる。さらに、ルールのある遊びで負け続けた幼児が相手を叩くなどの「いざこざ」が発生した場合、保育者が言い分を聞き合い、感情を言葉にする手助けを行うことで、葛藤解決や共感、行動の振り返りが促される。このような体験は、幼児が自ら問題を解決し、遊びを継続する力を育む契機となる。
保育者の役割は、幼児が安心して活動できる環境を提供し、適切な援助を行うことである。まず信頼関係の構築が重要であり、幼児が受け入れられていると感じることで主体的な活動が可能となる。主体性を尊重し、葛藤や挫折を経験させる際には、すぐに介入せず、子ども同士で解決しようとする過程を見守る姿勢が求められる。また、感情が高まる場面では保育者が子どもの思いを代弁することで、相手の立場を理解するきっかけを提供する。特に入園当初や言葉で自己表現が未熟な子どもには、仲介役として援助することが重要である。さらに、活動の発展を促す援助として、解決方法の提案や協力・達成感の共有が挙げられる。保育者は、個々の思いや活動をつなぎ、集団の中で個人の良さが生かされる環境を構成することで、幼児同士が関わり合える場を整える。
以上のように、乳幼児期の遊びは単なる活動ではなく、協力や譲り合いを学ぶ社会性の育成の場である。保育者は、温かく見守り適切に援助することで、幼児が葛藤や喜びを通じて主体性を発揮し、豊かな人間関係を築くことを支援することが求められる。
遊び例
0歳〜2歳(乳児期・幼児期前期の入口)
| 年齢 | 遊び例 | 発達の特徴 | 保育者の援助 |
|---|---|---|---|
| 0〜2歳 | 見立て遊び(ぬいぐるみに食事をあげる)、順番におもちゃを使う、手をつないで動く遊び | 他者への興味が芽生え、模倣や共有の経験が増える。自己中心的傾向が強い。 | 手本を見せる、順番や共有を声かけで伝える、安心感を提供する |
- 発達の背景: 幼児期は、保護者や周囲の大人との愛情ある関わりの中で見守られているという安心感に支えられて行動範囲が家庭の外へと広がり始めます。この時期の遊びにおいては、まず教師との信頼関係が築かれることが、幼児が心が安定し、積極的に周囲に関わるための基盤となります。
- 遊びの意義: 幼児は、教師などの親しみをもっている大人の行動を模倣し、同じようなことをやってみようとすることが多いです。
- 保育者の援助(安心感の提供): 教師は、幼児の行動や心の動きを温かく受け止め、理解しようと努めることによって信頼の絆が生まれます。いつでも適切な援助が受けられるという安心感をもつことが、主体的な活動の基盤となります。
2歳〜3歳(幼児期前期)
| 年齢 | 遊び例 | 発達の特徴 | 保育者の援助 |
|---|---|---|---|
| 2〜3歳 | ごっこ遊び(お店屋さん、ままごと)、ブロックや積み木で共同制作 | 平行遊びから連合遊びに移行。自己主張と譲り合いの葛藤が出やすい | 言葉で気持ちを代弁する、仲介役として衝突を整理、成功体験を一緒に喜ぶ |
- 発達の背景: 幼児期は、他者と関わり合う生活を通して、他者の存在を意識し、自己を抑制しようとする気持ちが生まれる時期です。しかし、この時期はまだ自分の思いを言葉でうまく表現できない場合も多いです。
- 人間関係と葛藤: 自己主張のぶつかり合いや、友達と折り合いを付ける体験を重ねながら友達関係が深まっていきます。
- 遊びの発展: 言語能力の発達は、見立てやごっこ遊びという活動の中で想像力を豊かにし、それを表現することを通して促されます。
- 保育者の援助(仲介・言葉の代弁): 自分の思いが相手に伝わらずに困る場面では、教師が仲介役となり、その思いを伝えることが必要となります。教師がその思いを的確に言葉で表現していくことで、幼児は表現しようとする内容をどう表現すればよいかを学んでいきます。また、いざこざが生じた場合、教師はそれぞれの幼児の主張や気持ちを十分に受け止め、互いの思いが伝わるように援助することが必要です。
3歳〜4歳(幼児期中期)
| 年齢 | 遊び例 | 発達の特徴 | 保育者の援助 |
|---|---|---|---|
| 3〜4歳 | ケーキ屋さんごっこ、警察ごっこ、段ボールでの共同制作 | 役割分担やルールを理解、協力して活動を楽しむ。相手の気持ちを意識する力が育つ | 葛藤時に子どもの気持ちを橋渡しする、解決方法を提案する |
- 遊びの意義: 段ボールの家を作る遊びのように、共同で作業を進める中で、幼児たちは自分のイメージを言葉や身体の仕草などを用いて伝え合います。相互に伝え合う中で、相手に分かってもらえるように自分を表現し、相手を理解しようとする力が養われます。
- 人間関係の深化: 友達と遊ぶ中で、自分の気持ちを調整し、相手と楽しく遊んだり生活したりできるようになります。また、友達と遊ぶ楽しさを経験するうちに、友達と一緒に物事をやり遂げたいという気持ちが強まっていきます。
- 保育者の援助(提案と承認): 幼児が遊びを持続し発展させようとする際、うまくいかなくなって諦めてしまいそうなとき、教師が適切な援助を行うことで、諦めずにやり遂げることができます。また、やり遂げたことを共に喜び、十分に認めることが、自立心や責任感を育みます。
4歳〜5歳(幼児期中期〜後期)
| 年齢 | 遊び例 | 発達の特徴 | 保育者の援助 |
|---|---|---|---|
| 4〜5歳 | 大型ブロックで町作り、劇ごっこ、ルールのある集団遊び(鬼ごっこ、かくれんぼ) | 協力・交代・交渉などの社会性が発達。友達関係がより複雑で深くなる | 集団ルールを確認しつつ自主解決を見守る、達成感や成功体験を共有 |
- 発達の特性: 幼児期は、他者との関わり合いの中で、様々な葛藤やつまずきなどを体験することを通して、将来の善悪の判断につながる基本的な区別ができるようになる時期です。
- 遊びの発展と社会性: 友達との関わりを通して、互いの違いや多様性に気付くことが大切です。共通の目的を見いだし、それに向かって工夫したり、協力したりするようになります。
- 保育者の援助(見守りと葛藤の活用): 幼児の主体的な活動を促すためには、教師がすぐに援助することによって幼児が自ら工夫したり、友達と助け合ったりする機会がなくなることもあるため、援助のタイミングを考える必要があります。葛藤の体験は幼児にとって大切な学びの機会であり、いざこざや言葉のやり取りが激しかったり、長い間続いたりしている場合に仲立ちをすることも大切です。
5歳〜6歳(幼児期後期/修了時)
| 年齢 | 遊び例 | 発達の特徴 | 保育者の援助 |
|---|---|---|---|
| 5〜6歳 | チームでのゲームやスポーツ、共同制作、長めのごっこ遊び | 役割意識が高まり協同・計画性を伴った遊びが可能。共感や自己抑制も発達 | 複雑な葛藤の整理・仲介、集団で個々の良さを活かす環境整備、発展的活動の提案 |
- 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」との関連: この時期は、幼稚園修了時に期待される姿として**「協同性」**が明確にされています。幼児は、共通の目的の実現に向けて、考えたことを相手に分かるように伝えながら、工夫したり、協力したりし、充実感をもって幼児同士でやり遂げるようになります。
- 道徳性・規範意識: いざこざを乗り越える体験を重ねることを通して人間関係が深まり、友達や周囲の人の気持ちに触れて共感したり、相手の視点から自分の行動を振り返ったりする姿が見られるようになります。
- 計画性と協同: 幼児たちは共同制作(例:段ボールの家作り)において、作ろうとする家のイメージを描き、作業の段取りを立て、手順を考えるというように思考力を働かせます。
- 保育者の援助(集団の質の向上): 教師は、一人一人の思いや活動をつなぐよう環境を構成し、集団の中で個人の良さが生かされるように、幼児同士が関わり合うことのできる環境を構成していくことが必要です。特に協同性が育まれるためには、それぞれの持ち味が発揮され、互いのよさを認め合う関係ができてくることが大切です。
保育内容「人間関係」 理論から実践まで (KS専門書)