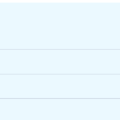「保育内容C(環境)」の授業①概要まとめ
1. 幼稚園教育の意義と保育内容
- 幼稚園は生涯の発達の基礎を育む場であり、遊びを通じて見通しある実践(指導計画)を行う。
- 保育内容は子どもに経験してほしいことを示すもので、成長の土台となる。
2. 発達の要因:遺伝と環境
- 発達には**成熟(遺伝)と学習(環境)**が関わる。
- 両者の相互作用説が主流。
- 野生児の例(アヴェロンのヴィクトール、カマラとアマラ)は環境の重要性を示す。
3. 幼稚園教育の基本
- 学校教育法に基づき、「環境を通して行う教育」が基本。
- 幼児の心身の発達を助長し、義務教育の基礎を築く。
- 小学校との違い:
- 興味・関心重視、直接体験を通じた学び
- 「感じる」「味わう」などの目標
4. 幼稚園教育要領と5領域
- 幼稚園教育は「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の5領域で構成。
- 領域「環境」では、以下を育む:
- 自然に親しみ、興味関心をもつ
- 自ら関わり、発見・探究し生活に活かす
- 物や数、文字への感覚を豊かにする
5. 子どもを取り巻く課題
- 現場の課題:基本的生活習慣の未発達、活動への消極性、情緒面の不安定さ。
- 社会的背景:
- 三間の喪失(時間・空間・仲間)
- 遊びの質の変化(自然・手作り→デジタル・個人化)
- 地域との関係の希薄化
- 核家族化、都市化、子ども産業の拡大など
6. 未来社会と幼児教育の役割
- 子どもたちは将来、今ない職業に就く可能性もある。
- 幼児教育では以下の資質・能力の育成が求められる:
- 知識・技能の基礎(気づき・理解・できる体験)
- 思考力・判断力・表現力の基礎(考え・試す・工夫)
- 学びに向かう力・人間性(意欲・態度・他者と協同)
- 目指す幼児像(10の姿):「健康な心と体」「自立心」「協同性」など。
①テスト
■設問①
「文部科学省が示しているもので、各幼稚園がしたがわなければならない保育内容に関する基準」
→ 答え:幼稚園教育要領
■設問②
「幼稚園教育要領には、発達を見る5つの視点である( 1 )について詳細な記述がある。」
→ 答え:(1)領域
■設問③
「現在では、( 1 )的要因と環境的要因が相互に働き合って発達するという( 2 )説が主流になっている。」
→ 答え:
(1)遺伝
(2)相互作用
■設問④
「人間として生きていくうえでは、生後間もなくから( 1 )期まで、その( 2 )からどのような影響を受けたのか、( 2 )とどう関わったのか、( 2 )との関わりから何を( 3 )、なにを( 4 )に付けたのかということが、( 5 )として生きていくうえで極めて重要である。」
→ 答え:
(1)乳幼児
(2)環境
(3)学び
(4)身
(5)人間
②テスト
教育に関する空欄補充問題(2017年改訂 幼稚園教育要領)
問題:
A)幼児の( 1 )としての遊びを生み出すために必要な( 2 )を整える
B) ( 3 )的な環境の構成
C) ( 4 )を工夫し、物的・( 5 )的環境の構成
選択肢:
ア)模倣 イ)自発的な活動 ウ)自由 エ)空間 オ)計画 カ)夢 キ)費用 ク)教材 ケ)環境
答え:
- (1)イ:自発的な活動
- (2)ケ:環境
- (3)オ:計画
- (4)ク:教材
- (5)エ:空間
2】現代の子どもの育ちの現状(〇・×問題)問題と答え:
- 他人と手をつなぐことができない → 〇
- 活動に消極的である → 〇
- 基本的生活習慣が非常によく身に付いている傾向にある → ×
- ちょっとしたことでキレやすい → 〇
- 地域でよく群れて遊ぶ → ×
- 初語を発する時期がはやくなっている → ×
3】子どもを取り巻く環境(〇・×問題)
問題と答え:
- 少子化・都市化 → 〇
- 1世帯における家族数の増加 → ×
- 就園率の低下 → ×
- 地域の人間関係が濃密 → ×
- 子どもだけで遊べる空間が増加している → ×
- 子どもの遊べる時間が多くなっている → ×
- 子ども産業の増加 → 〇