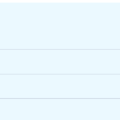レポート作成において、内容理解のためのメモ。
幼稚園教育における言葉の指導の基本的な考え方
- 環境を通して行う教育であること: 幼児は、生活を通して身近なあらゆる環境からの刺激を受け止め、自分から興味をもって環境に主体的に関わりながら、様々な活動を展開する中で言葉を獲得していきます。幼稚園は、幼児期にふさわしい生活を実現し、その発達を可能にする場であり、教育内容に基づいた計画的な環境をつくり出し、幼児が主体性を十分に発揮して展開する生活を通して、望ましい方向に向かって幼児の発達を促すことが基本となります。教師自身も豊かな言語環境となることを自覚し、幼児の身近なモデルとして言葉遣いや行動で影響を与える重要な役割を果たします。
- 遊びを通しての総合的な指導であること: 幼児期の生活のほとんどは遊びによって占められており、遊びは心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習です。言葉の獲得も、遊びや生活の様々な場面で行われる具体的な活動を通して、他の様々な能力と相互に関連し合いながら総合的に指導されます。例えば、友達との関わりの中でコミュニケーションを取ろうとする必要感から言葉による表現力が育ったり、ごっこ遊びの中で想像力を言葉で表現することを通して促されたりします。
- 一人一人の発達の特性に応じた指導であること: 幼児の言葉の発達には大きな個人差があります。一人一人の家庭環境や生活経験が異なるため、環境の受け止め方や関わり方も異なります。教師は、幼児一人一人の発達の実情(興味や関心、経験など)を理解し、それぞれの発達の課題に即したきめ細かな指導を行うことが大切です。また、言葉だけの発達ではなく、感情や思考など、精神諸機能の発達との関連においても捉える必要があります。
言葉の指導における重要な視点や基本的な考え方(内容の取扱いより抜粋)
- 人との温かい触れ合いの中での言葉の獲得: 言葉は、身近な人(教師や友達、家族)との温かい人間関係や心のつながりを基盤として、親しみをもって接し、自分の感情や意志を伝え、相手がそれに応答することを通して次第に獲得されていきます。教師は、幼児が心を動かされるような体験をし、言葉を交わす喜びを味わえるよう、温かい人間関係づくりに努める必要があります。言葉以外の非言語的なコミュニケーション(泣き声、表情、身振りなど)にも応答することが、その後の言葉の発達の支えとなります。
- 伝え合いの喜びを味わう: 自分の思いや考えを言葉で表現し、教師や友達が話を聞いてくれる中で、言葉のやり取りの楽しさを感じ、伝え合う喜びを味わうことが重要です。また、相手の話を注意して聞くことを通して次第に話を理解し、伝え合いができるようになっていきます。
- 経験と結びついた言葉の育ち: 幼児は、自分が経験したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えたりしたことを自分なりの言葉で表現します。様々な体験を通じて得た具体的なイメージが心の中に豊富に蓄積されることが、生き生きとした言葉の獲得や言葉の感覚を豊かにする上で大切です。絵本や物語などに親しみ、内容を自分の経験と結び付けたり、想像を巡らせたりすることも、豊かなイメージや言葉に対する感覚を養います。
- 言葉の楽しさや美しさに気付く: 単に言葉の意味を覚えるだけでなく、生活の中で言葉の響きやリズム、新しい言葉や表現に触れ、これらを使う楽しさを味わえるようにすることが言葉の感覚を豊かにします。絵本や物語、言葉遊びなどを通して、言葉が豊かになるように促します。
- 文字などへの興味・関心: 日常生活の中で、文字などが様々なことを表現するためのコミュニケーションの道具であることに自然に気付き、興味や関心をもつように促します。文字を道具として使いこなすこと自体を目的とするのではなく、人に思いなどを伝える喜びや楽しさを味わえるように援助することが重要です。
これらの考え方は、幼稚園教育全体を通じて、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の一つである「言葉による伝え合い」を育むことにつながります。教師は、これらの視点を念頭に置きながら、幼児の遊びや生活の過程を丁寧に捉え、一人一人の発達に必要な体験が得られるよう、環境構成や援助を工夫することが求められています。
乳幼児期の言葉の発達を促す上で、保育者の具体的な役割や環境構成は何か
保育者(教師)の具体的な役割
言葉の育ちを促す上で、保育者(教師)は以下のような様々な役割を担います。
- 温かい人間関係・信頼関係の構築: 言葉は、身近な人(教師や友達)との温かい人間関係や心のつながりを基盤として獲得されていきます。乳児期には、言葉以外の非言語的なコミュニケーション(泣き声、表情、身振りなど)にも応答することが、その後の言葉の発達の支えとなります。幼児は、教師との信頼関係を基盤に、自分の思いや考えを伝えたいという気持ちを膨らませ、言葉を発していくようになります。教師は、幼児が安心して自己を発揮し、温かい人間関係の中で言葉を交わす喜びを味わえるよう努める必要があります。
- 幼児の言葉や表現を受け止め、応答すること: 幼児が自分なりの言葉や非言語的な表現で何かを伝えようとしたとき、保育者(教師)がそれを受け止め、言葉にして応答することで、幼児は伝え合う喜びや表現する面白さを感じます。
- 幼児の身近なモデルとなること: 教師自身も豊かな言語環境の一部です。教師の日々の言葉遣いや行動は、幼児の言動に大きく影響を与えるため、正しく分かりやすい言葉で話したり、美しい言葉を使ったり、丁寧な文字を書いたりするなど、幼児に良い影響を与えるような関わり方を工夫することが大切です。
- 伝え合いの喜びを味わえるような援助: 自分の思いや考えを言葉で表現し、教師や友達が話を聞いてくれる中で、言葉のやり取りの楽しさを感じ、伝え合う喜びを味わえるように援助します。相手の話を注意して聞くことを通して次第に話を理解し、伝え合いができるようになっていきます。言葉が伝わらないときや分からないときには、状況に応じて教師が仲立ちをして言葉を付け加えたり、思いを尋ねたりすることで、話が伝わり合うよう援助することも重要です。
- 様々な体験と言葉を結びつける援助: 幼児は、自分が経験したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えたりしたことを自分なりの言葉で表現します。様々な体験を通じて得た具体的なイメージが心の中に豊富に蓄積されることが、生き生きとした言葉の獲得や言葉の感覚を豊かにする上で大切です。教師は、幼児が心を動かされるような体験(自然との触れ合いなど)をし、それを言葉で表現することを促すことが重要です。
- 言葉の楽しさや美しさに気付かせる援助: 生活の中で言葉の響きやリズム、新しい言葉や表現に触れ、これらを使う楽しさを味わえるように促します。絵本や物語、言葉遊び(しりとり、カルタ作りなど)などを通して、言葉が豊かになるように促すことも効果的です。
- 文字などへの興味・関心を促す援助: 日常生活の中で、文字などが様々なことを表現するためのコミュニケーションの道具であることに自然に気付き、興味や関心をもつように促します。文字を道具として使いこなすこと自体を目的とするのではなく、人に思いなどを伝える喜びや楽しさを味わえるように援助することが重要です。
- 幼児一人一人の発達や特性に応じたきめ細かな援助: 幼児の言葉の発達や生活経験には個人差があります。教師は、一人一人の発達の実情(興味や関心、経験など)を理解し、それぞれの発達の課題に即したきめ細かな指導を行うことが大切です。
- 幼児の活動(遊びや生活)を理解し、必要な時に適切な援助を行うこと: 幼児の活動には、一人一人にとって固有の意味があります。教師は幼児の活動を理解し、やりたいことが十分にできなかったり、困難に直面したりしている場合に、自信を失わないよう必要な援助をします。援助のタイミングや仕方は、幼児の自立心を育てる上で重要です。
環境構成の具体的な方法
言葉の育ちを促すためには、教育内容に基づいた計画的な環境をつくり出し、幼児が主体的に活動を展開できるような環境構成が基本となります。
- 主体的な活動が生まれる環境: 幼児が興味や関心をもち、主体的に環境に関われるよう、物的環境(遊具、用具、素材)、人的環境(教師、友達)、自然的環境(自然事象)、社会的環境(社会事象)などの様々な要素を関連付けて構成します。
- 言葉に触れる機会を豊富に設ける: 絵本コーナーの設置や読み聞かせ、言葉遊びができるような遊具や素材の準備、歌やリズム遊びを取り入れることなど、幼児が言葉に親しめる環境を工夫します。
- 文字などが自然に存在し、その役割に気付けるような配置: 日常生活の中で、標識や絵本、手紙など、文字や記号がコミュニケーションの道具として使われていることに気付けるように環境を構成します。
- 伝え合いが生まれやすい雰囲気や場の設定: 教師や友達と気軽に言葉を交わすことができる雰囲気や、落ち着いて皆で話を聞くことができる場(集まりの場など)を設定します。
- 様々な素材や用具を用意し、表現を促す: 音や形、色、手触りなど、様々な感覚を刺激する素材や、表現活動に使える遊具や用具を豊かに用意し、幼児がイメージを広げ、自分なりに表現を楽しめるようにします。
- 自然環境の活用: 風の音、雨の音、草や花の形や色など、身近な自然の中にある音や形などに気付き、それを言葉で表現したり、歌にしたりする活動に繋がるように、自然に触れる機会を多く設けることも重要です。
- 幼児の活動や発達に応じて柔軟に環境を再構成すること: 構成された環境は一時的なものと考え、幼児の活動の流れや心の動きに即して、常に適切なものとなるよう環境を再構成していくことが求められます。
これらの保育者(教師)の役割と環境構成は、一人一人の幼児が、人との温かい触れ合いの中で言葉を交わす喜びを味わい、様々な体験を通して言葉の感覚を豊かにし、経験したことや考えたことを言葉で伝え合い、言葉による伝え合いを楽しむようになるために不可欠です。これは「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の一つである「言葉による伝え合い」を育むことにも繋がります。
なお、言葉の発達は、家庭環境や生活経験によって個人差が大きいため、家庭との連携を密にし、一人一人の実情に応じた指導を行うことが重要です。また、特別な配慮を必要とする幼児に対しては、個別の教育支援計画や指導計画を作成・活用し、関係機関と連携した組織的・計画的な支援が必要です。外国人幼児など、生活に必要な日本語の習得に困難のある幼児に対しても、個々の実態に応じた指導内容・方法の工夫が必要です。
言葉の指導において、絵本や児童文化財をどのように活用できるか
乳幼児期の言葉の指導において、絵本や児童文化財は非常に重要な役割を果たします。幼稚園教育は、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うことを基本としており、幼児は生活や遊びを通して言葉を獲得していきます。言葉の発達は、知的な発達、社会性、感情、イメージ、認識などの精神諸機能とも関連しており、心身全体の発達と密接に関わっています。
絵本や児童文化財の活用意義
絵本や物語などの児童文化財に親しむことは、幼児の言葉の育ちを促す上で特に重視されています。その意義は多岐にわたります。
- 言葉に対する感覚を豊かにする:
- 絵本や物語を聞く中で、言葉の響きやリズム、新しい言葉や表現に出会い、これらを使う楽しさを味わうことができます。
- 語り継がれてきた作品には、美しい言葉や韻を踏んだ言い回しが多く使われており、幼児が自然に言葉を獲得していくのを助けます。
- 様々な体験を通じて心に蓄積された具体的なイメージが、生き生きとした言葉の獲得や言葉の感覚を豊かにする上で大切ですが、絵本や物語はこのようなイメージを一層豊かに広げます。
- 想像力や表現力を育む:
- 絵本や物語などで見たり聞いたりした内容を、自分の経験と結び付けながら想像したり、表現したりすることを楽しむことができます。
- 物語の登場人物になりきったり、自分たちの物語をつくって演じたりするなど、様々な表現を楽しむ活動につながります。これは、言葉による伝え合いだけでなく、感性や表現力の基盤を培います。
- 伝え合う喜びを味わう機会となる:
- 教師や友達と一緒に絵本を見たり聞いたりすることは、皆で同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感を生み出します。
- 絵本や物語の内容について友達や教師と話し合うことは、経験したことや考えたことを言葉で伝え合い、相手の話を聞いて理解する 機会となり、言葉による伝え合いを楽しむことにつながります。
- 感情や思考を深める:
- 物語の世界に浸る体験は、幼児に驚き、不思議さ、喜び、悲しみ、怒りなど様々な感情を体験させ、他人の痛みや思いを知る機会にもなります。
- 絵本や物語に関心を持つことで、なぜ、どうしてという疑問を感じ、思考力を働かせる基礎を培います。
- 多様な言葉や世界に触れる:
- 家庭では触れる機会の少ない多様な内容に触れる機会となり、幼児の興味や関心を広げます。
- 様々な言葉や表現、言い回しに出会うことで、語彙が豊かになります。
保育者(教師)の具体的な役割
絵本や児童文化財を効果的に活用するために、保育者は以下のような役割を担います。
- 温かい人間関係・信頼関係の構築: 幼児が安心して言葉を交わせる雰囲気や、気軽に言葉を交わすことができる信頼関係を築くことが基盤となります。教師との信頼関係は、幼児が自分の思いや考えを話したい、伝えたいという思いを膨らませる支えとなります。
- 幼児の言葉や表現を受け止め、応答すること: 幼児が自分なりの言葉や非言語的な表現で伝えたこと(絵本や物語から感じたことなど)を受け止め、言葉にして応答することで、伝え合う喜びや表現する面白さを感じられるようにします。
- 自ら言葉や表現を楽しむモデルとなること: 教師自身が言葉や表現を楽しむ姿を見せることで、幼児は言葉に親しみ、使ってみようという意欲を持つようになります。絵本を読む際に声のトーンや視線、手振りなどを工夫したり、抑揚をつけたり間をとったりする ことで、言葉のリズムや面白さを感じさせます。
- 絵本や物語の世界への導入・共感: 絵本の世界に入りやすいように幼児の経験を思い出させたり、幼児の感じ方や楽しみ方を大切に受け止め、共感する ことが重要です。教師が心を傾けて幼児の話やその背後にある思いを聞き取る ことも大切です。
- 伝え合いを促す援助: 絵本や物語の内容について、幼児同士の話し合いを促したり、必要に応じて言葉を付け加えたり思いを尋ねたりして、話が伝わり合うよう仲立ちをします。
- 文字などへの興味を促す: 絵本や紙芝居の文字に触れることで、文字が様々なことを表現するためのコミュニケーションの道具であることに自然に気付き、興味や関心を持つように促します。文字を道具として使う楽しさを味わえるように援助することが重要です。
- 様々な体験と言葉を結びつける: 絵本や物語の内容を、幼児の実際の体験と結びつけたり、それらの体験を言葉で表現することを促したりします。例えば、自然体験で感じたことを絵本の話と関連付けたり、砂遊びで感じた「さらさら」「ざらざら」といった言葉に関心を持たせるために絵本を活用する ことなどが考えられます。
- 一人一人の発達や特性に応じた援助: 幼児の言葉の発達や興味・関心には個人差があります。一人一人の実情に応じたきめ細かな指導を行い、無理なく言葉に親しめるよう丁寧に援助することが必要です。例えば、話すことに戸惑いがある幼児には、安心して発表できる環境を作ったり、言葉を補ったりする援助が考えられます。
環境構成の具体的な方法
絵本や児童文化財を活用した言葉の指導を促すためには、以下のような環境構成が考えられます。
- 言葉に触れる機会を豊富に設ける: 絵本コーナーを設置し、幼児が自由に絵本を見たり、教師が読み聞かせをしたり、紙芝居や物語を聞かせたりする機会を設けます。歌やわらべうた、言葉遊び(しりとり、言葉集め、カルタ作りなど)を取り入れることも有効です。
- 落ち着いて言葉の世界に浸れる場を設定する: 絵本コーナーなど、落ち着いて絵本を見たり聞いたりできる静かで安心できる場を設けます。集まりの場などで皆で一つの話を聞く機会を持つことも重要です。
- 文字などが自然に存在し、その役割に気付けるような配置: 絵本、手紙、標識など、日常生活の中で文字がコミュニケーションの道具として使われていることに自然に気付けるように環境を構成します。幼児が文字を使って伝えたい思いを表現できるような素材(紙、ペンなど)を用意することも考えられます。
- 表現を促す様々な素材や用具を用意する: 音や形、色、手触りなど、様々な感覚を刺激する素材や、絵を描く、物を作る、演じるなどの表現活動に使える遊具や用具を豊かに用意し、幼児がイメージを広げ、自分なりに表現を楽しめるようにします。
- 伝え合いが生まれやすい雰囲気や場の設定: 教師や友達と気軽に言葉を交わすことができる雰囲気や、落ち着いて皆で話を聞いたり伝え合ったりすることができる場を設定します。話し合いがしやすいように、場や物の配置を工夫することも有効です。
- 幼児の活動や発達に応じて柔軟に環境を再構成すること: 構成された環境は一時的なものと考え、幼児の活動の流れや心の動き、興味・関心に即して、常に適切なものとなるよう環境を再構成していくことが求められます。
これらの役割や環境構成を通じて、保育者は幼児が言葉を楽しみ、豊かに育んでいく過程を支えます。特に絵本や児童文化財は、幼児が言葉の世界に触れ、想像力を広げ、他者と心を通わせるための強力なツールとなります。指導計画を作成する際には、絵本の読み聞かせなどの活動を通してどのような言葉の育ちを期待するのか、具体的なねらいを明確に設定し、それに基づいて環境構成や教師の援助を計画することが大切です。
予想問題
① 幼児の言語発達に関する理論・特徴
幼児期の言語発達の特徴とその背景について、発達理論に基づいて説明しなさい。
幼児期の言語発達は急速に進み、特に3~5歳にかけて語彙の拡大や文法の獲得が著しい。ピアジェはこの時期を前操作期とし、自己中心的思考が特徴だが、言葉を通じて他者と関わる中で社会性が育まれる。ヴィゴツキーは、他者との相互作用の中で発達する「最近接発達領域」において、大人や友だちとのやりとりが言語能力を高めると述べている。
■非言語的コミュニケーションと幼児の言葉の育ちの関係について述べなさい。
幼児は言葉を十分に使えない時期に、表情や身振り、視線などの非言語的手段で意思を表現する。これらは他者との相互理解の基盤となり、言語習得への橋渡しとなる。保育者がこうした非言語的表現を受け止め、応答することで、幼児は「伝わる」喜びを感じ、言葉への関心や使用が促される。
■言葉の発達を支える保育環境の構成について述べなさい。
言語環境の整備として、絵本や図鑑、ポスターなど視覚的な刺激を用意することが重要である。また、子ども同士の会話が自然に生まれるような遊びのコーナーや、保育者が常に応答的な姿勢でかかわることも求められる。安心して発言できる心理的環境も大切であり、日常の中で子どもの言葉に丁寧に応じることが基本となる。
■問保育者は言葉の育ちにおいてどのような役割を果たすべきか述べなさい。
保育者は、子どもの発話のモデルとなるとともに、理解者、共感者としての役割を持つ。子どもの発言に耳を傾け、言葉を受け止めて返す応答的なかかわりが大切である。また、語彙の拡充や表現の幅を広げるために、適切な言葉かけや質問を行い、話し合い活動や絵本の読み聞かせを通じて豊かな言語経験を提供することが求められる。
■遊びの中で子どもの言葉が育つ場面と、それに対する保育者の関わり方を述べなさい。
ごっこ遊びなどの社会的遊びでは、子どもたちが役割を演じながら対話を重ね、自然な形で言葉のやりとりが生まれる。保育者は、子どもの発話をよく聴き、必要に応じて言葉を補完したり、新しい語彙を提示したりすることで、遊びの世界が広がり、言語的発展が促される。また、遊びの前後に子どもに話をさせる場を設けることも効果的である。
■日本語を母語としない子どもに対する保育者の言語支援の在り方を述べなさい。
文化的背景や言語習得の状況を理解し、安心して過ごせる環境を整えることが重要である。視覚的支援(写真・イラスト)や身体表現を活用し、非言語的手段でのやりとりを大切にする。保育者は繰り返しややさしい日本語を用いながら、子どもが自分の気持ちや考えを伝える機会を保障し、成功体験を積ませる、
■保育者自身の言葉遣いや態度が、子どもの言葉の発達にどのような影響を与えるか述べなさい。
保育者の言葉遣いや態度は、子どもの言語的・社会的学びのモデルとなる。丁寧で豊かな語彙を使った対話や、子どもを尊重した応答は、子どもにとって良質な言語環境を提供することになる。一方で、命令的・否定的な言葉かけは、表現意欲を低下させる可能性があるため、保育者は常に自らの言動を振り返り、子どもの模範となる姿勢が求められる。